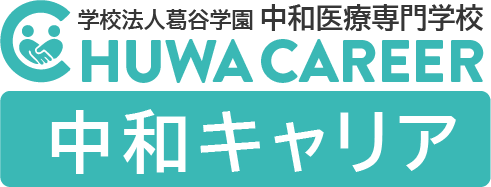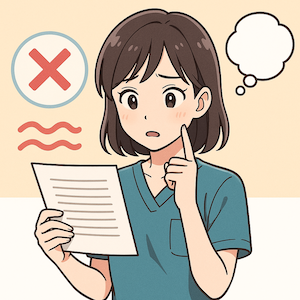臨床実習の経験をどう履歴書に落とし込むか?──“学校での学び”を言葉にする方法
はじめに
履歴書の「自己PR」や「志望動機」欄で、何を書けばいいか迷ったとき──
多くの学生にとって、最も説得力のある経験になるのが「臨床実習での学び」です。
でも、ただ「頑張りました」と書くだけでは、相手に伝わりません。
この記事では、実習の経験を履歴書にどう活かすか、具体的な整理のしかた・書き方をお伝えします。

なぜ実習の話が有効なのか?
- 学業の延長ではなく、“現場”での経験として評価されやすい
- 観察・判断・対応といった臨床的な視点が身についていることを伝えられる
- その施術所で働く姿をイメージしてもらいやすい
→ 学生でも「実務に近い経験がある」ことを伝える、貴重な材料です。
書く前に整理しておきたいこと
① どんな患者さんを担当したか?
(例:慢性腰痛、高齢者の関節拘縮、スポーツ外傷 など)
② どんな対応・サポートをしたか?
(例:問診補助、リハビリの誘導、物理療法の準備)
③ そのとき、どんな気づきや学びがあったか?
(例:声かけの大切さ、観察力、緊張との向き合い方)
→ 行動・結果・学びをセットで言語化しておくと、あとで書きやすくなります。
書き方のコツ
パターン① 自己PR欄で使う場合
臨床実習では、患者さんに安心してもらえるような声かけや表情づくりを意識しました。
はじめは緊張していた自分も、少しずつ「相手を見る」視点を持てるようになり、施術補助にも積極的に関われるようになりました。
→ 成長過程と姿勢を伝える構成が有効です。
パターン② 志望理由欄で使う場合
実習で慢性痛を抱える高齢者と関わった経験から、「生活に寄り添う施術」の大切さを実感しました。
貴院が掲げる「地域密着・対話を大切にする」という方針に強く共感し、ここで学び続けたいと思いました。
→ 実習経験と応募先の方針をつなぐことで、説得力が増します。
NG例と改善ポイント
- 「実習でいろいろ学びました」だけでは具体性ゼロ
- 「頑張った」「やりがいがあった」は抽象的すぎる
- 「○○を学びました」→“どう活かしたいか”がないと浅く見える
→ 体験→気づき→今後どうしたいか の流れがカギです。
まとめ
臨床実習の経験は、単なる「学校行事」ではなく、あなたの人柄や強みを伝える大事な武器になります。
小さな場面でも構いません。
自分の言葉で「何を感じて、どう動いたか」を書き出してみましょう。
それが、履歴書に“生きたエピソード”を加える第一歩になります。