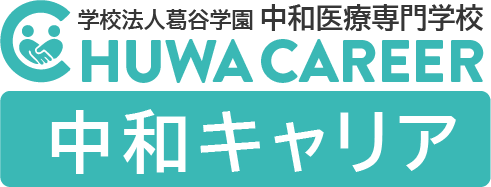印象を決める瞬間 ― 面接で伝えるべきこと
第一印象は準備で作れる
面接の成否を左右する最初の数十秒は、偶然ではなく準備の質で決まります。入室前の深呼吸、ノックの回数、姿勢と視線、第一声の明るさまでを“型”として体に入れておくと、緊張しても体が自動運転で動きます。服装と髪型は「清潔・整頓・機能性」を合言葉に。靴の手入れや書類の挟み方など、細部の整いはそのまま“仕事の丁寧さ”の代理指標です。医療系では患者さんに安心を与えられる人かが評価されるため、柔らかな表情と落ち着いたトーンで「この人に任せたい」を最初の一瞬で伝えましょう。鏡での所作チェック、動画撮影による自己観察、第三者フィードバックの三点セットを面接前日までに反復するのが実践的です。

志望動機は「共感→接続→貢献」で組み立てる
志望動機は“好きです”の感情表明ではなく、相手の方針に自分の経験と強みを論理で接続する説明です。まず求人や見学で得た事実から「共感した取り組み」を一つに絞って提示します。次に、実習・アルバイト・学内プロジェクトなどの具体経験を出して「自分は似た価値を実践してきた」ことを橋渡しします。最後に配属後の学習計画や担当領域での具体的貢献(例:患者説明の標準化、勉強会の運営補助、SNSでの啓発など)を一文で示すと、動機が意欲にとどまらず行動設計まで落ちています。文章にすれば三段で二百字、口頭なら六十秒以内。事前に音読し、語尾を言い切りで揃えると芯が通ります。
自己PRは“STAR”で短く深く
「強みは粘り強さです」だけでは伝わりません。**STAR(Situation/Task/Action/Result)**の順で、60〜90秒の小話に凝縮します。状況は15秒以内、課題は一言で、行動の部分に時間配分の六割を置き、工夫や判断の根拠を具体語で描写します。結果は数値・第三者評価・学びのいずれかで締め、最後に「その学びを御院ではこう活かす」と職務文脈に接続します。たとえば「高齢者向け説明で図解カードを自作→理解度アンケート上昇→院内共有資料の雛形に」という流れなら、面接官は“現場で再現可能な行動特性”として評価できます。メモにキーワードだけを書き、丸暗記は避け、語りの自然さを残すのがプロの仕上げです。
非言語を整える:声・間・視線・姿勢
内容が良くても、非言語が不一致だと説得力は落ちます。声量は小部屋で「遠くの相手にも届く程度」、語速はやや遅め、語尾は上げずに言い切る。一文一呼吸で間を置き、相手のうなずきを確認してから次に進みます。視線は面接官の目元—眉間—ノート—再び目元の三点をゆっくり循環させ、凝視や泳ぎ目を避けます。姿勢は坐骨で座り背中を長く、両足は床にフラット、手はテーブル上でペンとメモを基準位置に。医療接遇に通じる所作は、患者対応の適性シグナルとしても加点対象です。スマホ録画で5分の模擬面接を取り、音声は波形、姿勢は静止画で確認すると改善点が一目で分かります。
面接は終わってからが伸びる:即時リフレクション
退出後30分以内に、良かった点/改善点/次回の具体修正を三項目ずつメモします。良かった点は再現のための手順化、改善点は原因仮説と対策を次の練習予定に予約するところまでセットで。可能なら当日中に短いお礼メールで来社の感謝と学びを一行添えます(過剰に長文にしない)。不採用でも、録音や記録から“問いの意図”を再分析し、回答の構造をチューニングすれば、次回の通過率は着実に上がります。就活後半ほどメンタルの波が成績に直結するため、睡眠・食事・軽運動のルーティンで体調を平準化。準備→実践→振り返り→修正の短いPDCAを一回転させるたびに、面接は確実に“安全運転”になります。