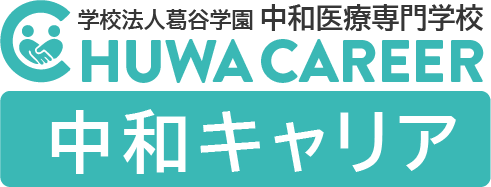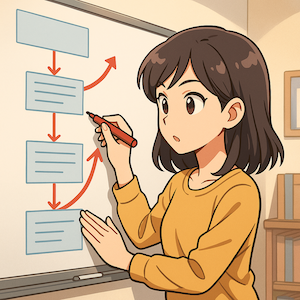キャリアの「軸」を築く ─ 専門職としての方向を見定める
働く目的を“自分の言葉”で定義する
キャリア設計の出発点は、「何のために働くのか」を明確にすることです。医療・福祉・スポーツなどの専門職は、人の生活や健康を支える使命を持つ職業です。しかし、同じ業界でも“誰のために、どう貢献したいのか”は人それぞれ異なります。たとえば、「痛みを取る技術を極めたい」「地域で安心できる治療を広げたい」「チーム医療の一員として支えたい」など、自分が惹かれるテーマを具体的に言葉にしていくことが大切です。その言葉が、将来の進路を決める指針=キャリアの“軸”になります。

「得意・苦手」と「好き・嫌い」を切り分ける
キャリアを考える上で、自分の得意分野を把握することは重要ですが、“得意=好き”ではありません。人によっては得意だけれど精神的に疲れる仕事もありますし、苦手だけれど挑戦していくうちにやりがいを感じる仕事もあります。自己理解のコツは、「できること」「やりたいこと」「やる価値を感じること」の3つを分けて考えること。それぞれを円で描き、重なる部分が“キャリアの中心”です。この整理を繰り返すことで、自分の働き方に合った方向が自然と浮かび上がります。
人生全体のバランスを見据える
キャリアは仕事だけではなく、生活や家族との関係、学び直しのタイミングなども含めて設計すべきものです。特に医療・福祉系では、勤務時間や責任の重さが日常生活に影響を与えることがあります。長く続けるためには、プライベートや健康、趣味とのバランスをどう取るかを具体的に想定しておくことが重要です。どれほど理想的な仕事でも、無理が続けば燃え尽きてしまいます。キャリア設計とは、理想と現実のバランスを“持続可能”に整える作業なのです。
10年先を想像して逆算する
5年後・10年後にどんな自分でありたいかを描くと、今やるべきことが明確になります。たとえば、「将来は独立開業したい」と思うなら、まずは臨床経験や経営知識を積む計画が必要です。「チームで活躍したい」なら、リーダーシップやコミュニケーションスキルの学びを優先するべきです。漠然とした夢も、時間軸を入れて分解すると行動計画になります。年単位ではなく、半年単位の小さなゴールを設定し、それを積み上げることで、現実的な成長ラインが見えてきます。
「軸」は固定ではなく進化する
学生時代に描いた理想が、実際の職場経験によって変わるのは自然なことです。成長するほど価値観は変化し、軸も深まります。だからこそ、“今の自分”にとっての軸を定期的に言語化することが大切です。毎年1回、自分のキャリアノートを見直す。そこに新たな目標や気づきを加え、古い考えを更新する。この繰り返しが、ブレない成長の秘訣です。キャリアとは完成形を目指すものではなく、変化を受け入れながら磨かれていく“プロセス”そのものなのです。