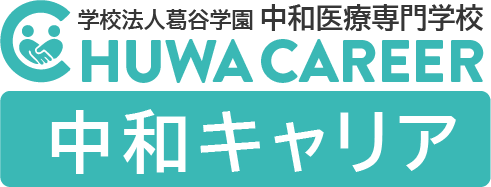なぜこの施術所?を“感情”でなく“根拠”で伝える──伝わる志望理由の作り方
はじめに
志望理由を書こうとして、つい「○○に共感しました」「雰囲気がよかったです」といった“ふわっとした感想”で終わってしまっていませんか?
たしかに共感や直感も大切ですが、
採用する側が見ているのは「なぜそう思ったのか」「どこに惹かれたのか」という“根拠”です。
この記事では、感情だけに頼らず、論理的に伝わる志望理由の作り方をお伝えします。
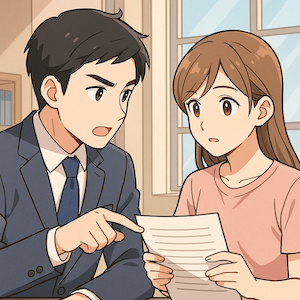
なぜ“感想”だけでは伝わらないのか?
- 「雰囲気がよかった」だけでは、他の院にも当てはまる
- 「共感しました」だけでは、その院である必然性が伝わらない
- 採用側は「うちで働きたい理由」を知りたい
→ 「この人は本気で調べてきたな」と思わせることがカギです。
“感情”から“根拠”へ──3つの切り口
① 実習や見学の体験を掘り下げる
例:
「○○の見学で、患者さんとスタッフの距離感がとても自然だったことが印象的でした。
私もあのように、緊張感を持ちつつも信頼関係を築ける施術者を目指したいと思いました。」
→ “どこに惹かれたか”を具体的に書きましょう。
② 施術所の方針・取り組みを調べて結びつける
例:
「SNSで『○○プロジェクト』を知り、地域に根ざした活動に力を入れている点に共感しました。
将来、地域医療に貢献できる施術者になりたい私にとって理想的な環境だと感じました。」
→ ホームページやブログ、インスタなど**“事前調査の結果”を示す**と説得力が増します。
③ 自分の学びや経験とつなぐ
例:
「実習で担当した高齢の患者さんとの関わりから、ただ施術するだけでなく生活全体を見る視点の大切さを感じました。
貴院が取り組まれている“生活支援型施術”に深く共感しています。」
→ “だからここで学びたい”という理由に結びつけることが大切です。
志望理由の構成テンプレート
- 【きっかけ】共感や印象に残ったこと
- 【深掘り】どのように感じたか、なぜそう思ったか
- 【接続】自分の経験・価値観とつなぐ
- 【展望】ここでどう成長したいか・どんな施術者を目指したいか
→ 感情+根拠+将来像がそろうと、“本気の志望理由”になります。
まとめ
「なんとなく好き」も立派な入り口です。
でも、そこから**「なぜそう思ったのか?」を言葉にしていくことで、伝わる志望理由に変わります。**
あなたの“気持ち”を“根拠あるメッセージ”に変える作業、
ぜひ一度、丁寧に取り組んでみてください。