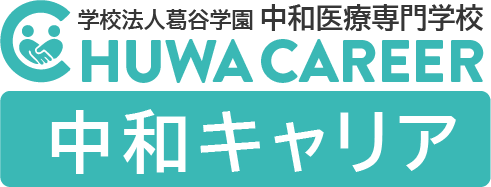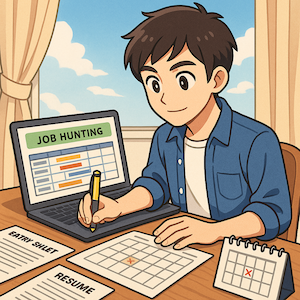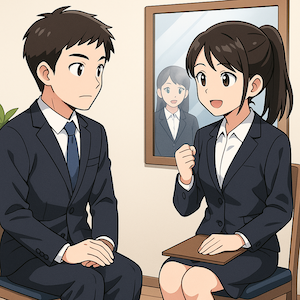採用担当者の心を動かす ― 書類作成の基本と工夫
「読む人」を意識した書類づくり
履歴書や志望動機書は、あなたの人柄を最初に伝える「顔」です。内容そのものよりも、まず目に入るのは「丁寧に作られているか」「読みやすいか」という印象です。乱れた字や余白の使い方一つで、“雑な人”という印象を与えてしまうこともあります。文字の大きさや行間を整え、余白をバランスよく配置するだけでも印象は格段に良くなります。採用担当者が数多くの応募書類を読むという現実を意識し、「短くても伝わる」構成を意識しましょう。

「なぜここで働きたいのか」を掘り下げる
志望動機では、「御社の理念に共感しました」「地域医療に興味があります」といった表現だけでは不十分です。大切なのは、その理念や取り組みを自分の経験とどうつなげて説明できるか。たとえば「学生実習で地域密着型の治療を経験し、患者との信頼関係づくりにやりがいを感じた。その経験を生かして、地域医療に貢献したい」というように、実体験をもとに語ると説得力が増します。
また、応募先の特徴(施術方針、対象年齢層、スタッフ構成など)を事前に調べ、それを踏まえた動機を記載すると、「理解して応募してくれている」と好印象を与えます。
自己PRは“行動”と“結果”で示す
自己PR欄では、「責任感がある」「粘り強い」といった抽象的な表現では伝わりません。
たとえば「実習中、施術計画の改善案を提案し、患者さんの回復ペースが早まった」「アルバイトで後輩指導を任され、全員が期日までに資格試験に合格した」など、行動→結果の流れで書くと、あなたの強みが具体的に伝わります。
また、失敗体験から学んだことを短く添えるのも有効です。「初めは患者対応で失敗したが、記録を見直し改善した結果、次第に信頼を得られた」というように、成長の過程を見せると印象が深まります。
丁寧な言葉づかいと表現の統一
文体は「です・ます」で統一し、略語や口語は避けましょう。「~とか」「~みたいな」といったカジュアルな表現は、たとえ話としても控えるのが無難です。
また、日付や学歴・資格の書き方にも注意が必要です。和暦・西暦を混在させず、時系列を整えることで“読み手に優しい書類”になります。封筒の宛名や送付状の敬語も軽視できません。応募書類全体が一つの作品であり、細部の整え方がそのまま社会人としての信頼感に直結します。
ミスを防ぐ“見直しルール”
提出前には必ず第三者に確認してもらいましょう。自分では気づかない誤字脱字や文の曖昧さを指摘してもらうことで、完成度が一段上がります。
また、印刷時には用紙の選択にも気を配ります。コピー用紙ではなく、少し厚めの上質紙を使うと、書類全体が引き締まった印象に。こうした小さな工夫の積み重ねが、最終的に「丁寧な人」という印象を生みます。
書類は“あなたの第一印象”を決める鏡
面接より前に採用担当者が接するのが、この書類です。書き方一つで、あなたの姿勢や価値観が伝わります。
「手を抜かず、心を込めて書く」――この当たり前の姿勢が、最も強いアピールになります。慌てず、焦らず、そして何より“自分らしい言葉”で仕上げましょう。