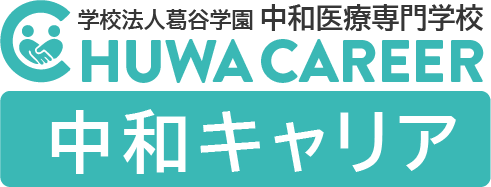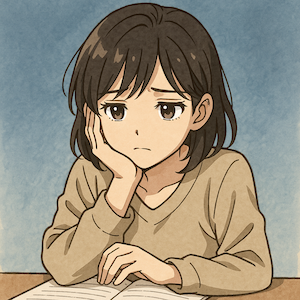未来をつくるのは「分岐点」──選択に迷ったときのキャリアマップ活用法
「迷い」は、成長のサイン
将来の方向性に迷うのは悪いことではありません。
むしろ、「本当にこの進路でいいのか」「もっと自分に合う道があるのでは」と立ち止まって考えられることは、キャリア設計において非常に大切な姿勢です。
迷うということは、自分の未来に責任を持ち始めている証拠でもあります。
そうした迷いを整理し、前向きな決断に変えていく道具として「キャリアマップ」が役立ちます。
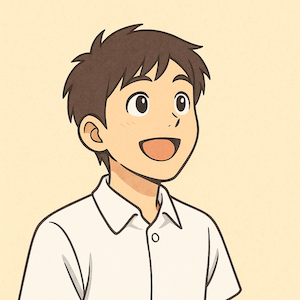
「AとB、どっちを選ぶべき?」ではなく、「どちらの道が何につながるか」
キャリアにおける選択肢は、単純な正解・不正解で分けられるものではありません。
たとえば「整骨院か、美容系鍼灸院か」「大手か個人院か」など、どちらを選ぶかで迷ったとき、それぞれの道がどんな経験につながり、どんな成長のチャンスがあるかを“地図上に並べてみる”ことが重要です。
それにより、「どっちが“今の自分”にとって適しているか」が明確になります。
未来を選ぶために、まず“選び方”を見える形にしておきましょう。
分岐点は「点」ではなく「線」で考える
キャリアマップを描く際に意識したいのは、「どの選択もその場限りではない」ということです。
たとえば、最初に整骨院に就職しても、美容系にキャリアをスライドすることは可能ですし、その逆も同じです。つまり、選択とは「ゴール」ではなく、「次につながる通過点」なのです。
「この道に行ったら終わり」と思うのではなく、「この道に行けば、次にどんな選択肢が広がるか」を考えることで、プレッシャーも軽くなります。
書いて、比べて、納得するプロセスが大切
頭の中で考えているだけでは、選択肢の整理は難しいものです。
紙に書く、マップとして図にする、友人や先生と話しながらアウトプットする──
そうした行動を通じて、モヤモヤが少しずつ言語化され、「自分が何を大事にしているのか」が見えてきます。
「どちらが正しいか」ではなく、「自分がどちらにワクワクできるか」や「不安が少ないか」といった感覚も、地図に残してみてください。
キャリアマップは「未来の自分」との対話ツール
キャリアマップを描くことは、未来の自分と対話することでもあります。
今、迷っていることも、半年後には「描いてよかった」「選んでよかった」と思える材料になっていきます。
進路に迷ったときこそ、キャリアマップに立ち返る。
それが、自分らしい選択を続けていくための道しるべになります。